この季節になると、街を歩いていて、はっと立ち止まる時がある。
ある日、突然、空気が香るのだ。
それは、オーストラリアのユーカリの大地のように大気全体が香るというわけではなく、街のあちこちに香りのかたまりが漂っていて、ふいにその中に入り込むと幸せなのである。
金木犀、その香りが覚えている風景がある。
秋は、豊橋にも芸術の調べを運んでくれる。昔、大手町の金毘羅神社の前には喫茶バロックがあった。今はもう、すっかり取り壊されて、モダンな歯科医院に変わってる。
喫茶バロックは、その名のとおり、お店の中にチェンバロやリュートだったか。古い時代の楽器が置かれていて、時々演奏会も開かれていただろうか。普段、芸術的な雰囲気に無関係だった田舎の少年には、店内に置かれている演劇雑誌や、クラッシック音楽の専門書などが醸し出すその雰囲気だけで芸術という文字を感じたものだ。そして、コーヒーポットで入れてくれるコーヒーは不思議とおいしく心が落ち着いた。
店主は当時、豊橋演劇塾という劇団を指導されていて、不器用で、無骨までに演劇を愛していた若者たちが、店主を慕って集まっていた。ある秋の日、私は豊橋祭りの喧騒を避けて、店でコーヒーを飲んでいた。詩集を読み、隣の席ではいつものように演劇塾の若者たちが次の舞台のことを熱く語っていた。やがて、店を出た。すると、どこからか金木犀の香りにすれ違った。
たった、それだけのこと
なのに、いまでもあの時の一瞬を懐かしく思い出されるのは何故だろう。もう40年以上前のことだ。
大手町には懐かしいものがたくさんあった。ペンショップオーテの巨大な万年筆の看板、
そして、今でも、東京庵本店から北に延びる大手通りの先には豊橋公会堂が立っている。昔はこの大手通に市内電車が走っていて、公会堂に向かって街が続いていく、そんな都市計画がなされていた。
私の人生の中では、この公会堂の改修と穂の国とよはし芸術劇場の整備と、動物園でのアジアゾウの新規導入が最も力を注いだ仕事だった。
豊橋公会堂はその表面を人造石洗い出し工法で作られている。これは、セメントなどに細かい大理石などを混ぜ、表面を研ぎだして、石を浮かび上がらせる工法で、昭和の初期まではよく使われていた工法である。私が公会堂の担当になった頃、表面の壁は雨水がしみこみ、所々浮き上がっては、剥落しているところさえあった。特に軍都豊橋を象徴した屋上の2羽の鷲のモニュメントは中の鉄筋が錆で爆裂しており、落下の危険性もあった。
公会堂の色は、洗い出し工法に使う石の色で決まる。当時の色を調べるために古老に聞き取りをして、使う石を決めた。本当に当時の色になったのか自信がなかったが、今はそれが伝統になっている。
公会堂から市電通りを隔てた豊橋調理師学校の南のあたりに、小さな空き地がある。
昔、ここに、ライブスタジオ?ミシシッピーがあった。すごく小さな店で、ビールと乾き物だけの、全く商売っ気のない店だった。知り合いの数人がジャズバンドを組んでよく演奏していた。店主もメンバーであり、みんなビールを飲みながら演奏し、渋いにいちゃんの、決してうまくないが、味のあるボーカルが好きだった。私は見たことはないが、演奏しながらメンバーが居眠りをすることもあったという。いいかげんなバンドだった。でも、そこの店でビールを飲み、いつもと同じジャズを聴きながら、ウイスキーを傾ける、そんな時間は、とても満ち足りていて、メンバーが演奏するときはちょいちょい顔を出した。秋のひんやりとした空気の中で残業を終え、金木犀の香りの中を急ぎ店のドアを開けると、そこには満ち足りた、一日の終わりがあった。
そして、やがて、店が閉まると聞いた時には、ある時代が終わってしまったような、不思議な虚無感があったのを覚えている。あの時のメンバーの一人とはロードバイクや山登りで今も一緒に遊んでいる。でも、もうあの不思議な時は帰ってくることはない。
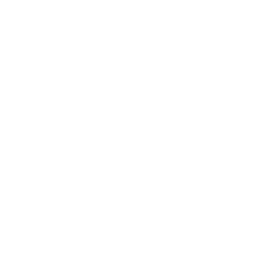



コメント