2021年 1月9日 松本~安曇野~大町 38㎞ 8h
松本平の向こうには、真っ白な北アルプスがそびえているはずだった。しかし、山々は雪雲に厚く覆われ、塩尻峠から顔を出した太陽はその雲を淡いオレンジに染め上げるだけで、この凍りついた大地を緩める力はないようだった。
-7度、風はないので、辛い寒さではない。私は再び歩き始める。
放浪の俳人、種田山頭火は、昭和5年の行乞記の冒頭でこんな言葉を残している。
「私はまた旅に出た、所詮乞食坊主以外の何物でもない私だった。愚かな旅人として放浪するより外に私の生き方はないのだ。水は流れる、雲は動いて止まない、風が吹けば木の葉が散る、魚行いて魚の如く、鳥飛んで鳥に似たり、それでは、二本の足よ、歩けだけ歩け、行けるところまで行け。」
この言葉には、一人で歩んでいく、そのかけがえのない孤独と、それゆえに出会う様々な風景の素晴らしさがある。心にしみいる言葉の響きが、たとえようもなく素敵だ。
淡々と、松本平と安曇野を分ける峠を目指す。松本という街は、古いものが、ごく当たり前に残っていて、集落を分ける道祖神や、古い社、自然石にまかれた縄、泉の傍らには水神があり、田畑の隅には必ず野神が祭られていた。 10分も歩けば、そういった神に出会うことができた。心はそのたびに祈りの言葉をそこに残し、通り過ぎていく。
10分も歩けば、そういった神に出会うことができた。心はそのたびに祈りの言葉をそこに残し、通り過ぎていく。
峠をこえると、そこには安曇野が広がっていた。初夏、尾根に伸びるアルプス公園から望む安曇野は田に水が張られ、それはそれは大きな水鏡となり、アルプスの残雪を抱いた姿をみごとに映しとっていた。でも、今は枯野が広がるばかり、ところどころに見える白い点は、犀川にやってきている、白鳥の群れだろう。
長い坂を安曇野に向かい降りていく、犀川にかかる長い橋を渡ると、そこには豊かな水路がめぐる湧水地が広がっている。 冬のこの時期でも、この湧水地には水があちこちで流れ、清潔な砂利が敷き詰められた川床には、鮮やかな色のわさび田が広がっていた。水の流れに光が輝くと、私の心にも青い空が広がるように思えた。手袋を脱いで、風景をひとしきり眺める。
冬のこの時期でも、この湧水地には水があちこちで流れ、清潔な砂利が敷き詰められた川床には、鮮やかな色のわさび田が広がっていた。水の流れに光が輝くと、私の心にも青い空が広がるように思えた。手袋を脱いで、風景をひとしきり眺める。
水色の時道祖神(1975年にNHKで放映されたテレビ小説の舞台として作成された。)、を過ぎると、光輝く水路のわきに、木造の小さなケーキ屋さんがある。たくさんのコレクションを誇るそのお店の裏、犀川の土手には早春賦の碑が小さなベンチをひかえ、立っている。この早春賦の碑の前のベンチに腰を掛け、よくさわやかな香りのケーキをいただいた。もう食べることのないその思い出を、水路に揺れる水草の脇に置いていく、そして、やがて犀川を後にする。
いくつかの長い橋を渡ると、池田町に入る。ハーブで有名な町だ。昨年の4月、ロードバイクに跨った私は、松本の娘の家から、木崎湖を目指し、この町を走っていた。町の右側には緩やかに丘が続いていて、桜の花のにじむような色が丘を覆っていた。
あの時と、今は、確実に何かが違う、ロードバイクで過ぎ去った町は、風景とは友達になったが、今、こうして歩いていると、もっと深く街と人々と語り合っている自分がいた。
やがて、少しずつ雪が出始める。最初は、雪面に足跡を残していく程度だったが、やがて、雪の深さは、くるぶしまでとなり、一歩一歩足元を確認しながら進んでいく。もともと、雪の上を歩くのは嫌いではない、冬の始めに新雪に覆われた登山道を簡単なラッセルで進んでいくのは心が躍る体験だ。
しかし、この道は、それとはだいぶ違っている。民家や事業所の回りは、雪が踏み固められ、氷となっている場所もあった。一方、人気のない歩道は、膝までの雪が残っており、雪をかき分け進むことも珍しくなかった。歩くスピードは格段に落ちていった。やがて、道路わきに雪が積み上げられ、通過する車が私を気にして、ゆっくりと隣を過ぎていくのがわかる。そして、大町のホテルを目の前にして、大きな陸橋の脇の雪は私の下半身をも埋めてしまい、泳ぐようにして、ホテルにたどり着く。年明け初めの道は、少し苦労した道だった。
けれども、私は再び歩き始めた。所詮歩くことしかできない私だった。
だれの心
この世の中に
こんなにも優しく
こんなにも美しく
こんなにも暖かい
この光はだれ
だれの心
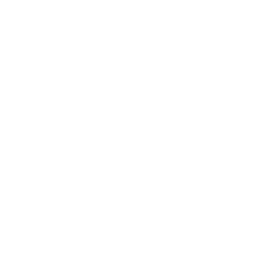



コメント